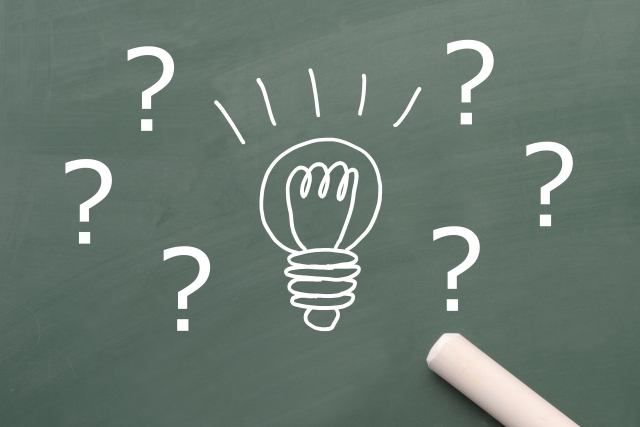
質問
Pusher現象のある患者さんの離床で、立位練習を行うコツはありますか?
回答
バイオメカニクスの観点からは、「視覚的フィードバック」と「床反力ベクトル」の活用がお勧めです。
「視覚的フィードバック」では、壁の近くで立位練習を行うことや、点滴棒を目の前に置くことで、患者さんに自身の身体の傾きが理解しやすいような、環境設定をすると、Pusher反応や姿勢の修正が行いやすくなります。
「床反力ベクトル」では、麻痺側の支持性がないと立位姿勢の修正は難しいため、長下肢装具を使用するのがお勧めです。その上で、非麻痺側の荷重ベクトルを、麻痺側に押すのではなく、非麻痺側に骨盤・体幹がシフトして、荷重を受けとめる感覚を繰り返し練習する必要があります。
さらに、立位練習の場面で、手で手すりや台を支持すると、Pushする反応が強くなる場合は、あえて非麻痺側上肢の支持はなしにして、荷重練習を行うことも有用です。
Pusher現象の重症度に応じて環境を工夫して、2つのポイントを意識してアプローチを行ってみてください。
6月15日(日) 10:00~16:00 ※2週間見逃し受講期間有り
バイオメカニクスを活かした理学療法の神髄~動作分析を最大限に用いたリハビリテーションの具体策~脳卒中編
講師:石井 慎一郎 先生
https://www.rishou.org/seminar/jitsugi/j24-2025#/
皆様の申し込みを心よりお待ちしております。
[脳卒中の離床・看護ケアを書籍で学びたい方は]
脳卒中急性期における看護ケアとリハビリテーション完全ガイド
https://www.rishou.org/publication/stroke#/




